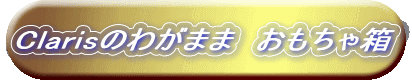
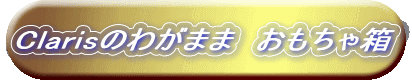
|
一つのハードディスクを論理的に区分けすることにより、複数のハードディスクが存在するように見せかけることが出来ます。 この区分けされた領域を”パーティション”と、いいます。 パーティションには、”基本パーティション”と”拡張パーティション”が有ります。 基本パーティションには、DOSやwindows95/98/MeのDOSブートローダーがどのパーティションの先頭に書かれたプログラムを呼び出すかを判断するためのフラグ:アクティブを設定することが出来ます。 一方、拡張パーティションには、このフラグは設定できません。 つまり、DOSやwindows95/98/Meのインストール先は、基本パーティションである必要があります。 (厳密には、C:\WINDOWS等は基本パーティションにインストールする必要と、言うことです。) Linuxの場合は、フラグ:アクティブが設定されていないパーティションからでも、起動できるので、拡張パーティションにもインストールすることが出来ます。 拡張パーティションの場合は、論理パーティションと呼ぶ仮想的なパーティションを内部に作成することが出来ます。 一つのハードディスクには、基本パーティションを最大4つしか作成できませんが、そのうち、一つを拡張パーティションとすることで、任意の論理パーティションを作成することが出来ます。 また、拡張パーティションは、1つのハードディスクに一つしか作成できません。 拡張パーティションのイメージ図 windows95/98/Meの場合は、最低一つの基本パーティションがあれば、O/Sをインストールすることが出来ます。 しかし、Linuxの場合は、パーティションが最低で二つ必要となります。 ・ルートパーティション ・・・ システムや各種ツール・アプリケーションを収める ・スワップパーティション ・・・ 仮想メモリーとして必要 windowsでもスワップと呼ばれる仮想メモリーを使用していますが、専用のパーティションが必要な訳けでは有りません。 |
|||||||||||||||||||||